
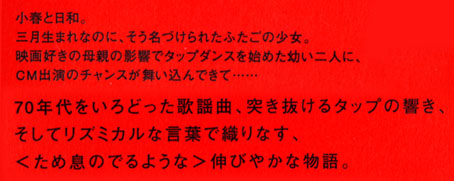
<文庫本>販売中
野中 柊 :著
出版社:集英社 (2006/3/17)
¥ 540 (税込)
<初版本>
野中 柊 :著
出版社:青山出版社 (2001/7/1)
¥ 1500 (+税)
ザ・ピーナッツ・ファンに贈る素敵なお話
 |
<文庫本>販売中 野中 柊 :著 <初版本> 野中 柊 :著 |
「ねえ。お父さん、知ってた? ザ・ピーナッツ引退しちゃうみたいだよ」
「ああ。そうだってなあ」父は表情ひとつ変えずに言った。
「な−んだ。知ってたの?」と食器を洗いながら小春が言った。
「そりゃあ知ってるさ」
「そりゃあ知ってるよね? お父さん、ファンだもんね」
「そうだな」
「ショックだった?」
「ああ。ショックだねえ。淋しいねえ」
そう言いながら、父は笑った。私はどうしてか少し悲しくなって、手を伸ばして父がくわえて
いる煙草を取った。そして、灰皿の緑で火をもみ消しながら、
「いいじゃん。お父さんにはあたしたちがいるから」と言った。
小春も流しから振り向いて言った。
「そうだよ。あたしたちがまた歌ってあげるよ」
父は、ははは、と取ってつけたように笑った。以前はよく父のリクエストに応えてザ・ピーナ
ッツを歌っていたものだったけれど、この頃はすっかりご無沙汰していた。ザ・ピーナッツの歌
詞が子供らしくない、と母にやりこめられて以来、二度と父は歌ってくれとは言わなくなったの
だ。私たちが、ね−ね−ザ・ピーナッツ聴きたい? と水を向けても、いや別に、とそっけない。
その態度は頑ななほどだった。意地になっていたのかもしれない。
「いいよ。いいよ。無理するな」と今度も父は言った。でも、いつもとは違って少し嬉しそうに
笑みを浮かべ、「おまえたちは意外に親孝行だな」
「そうだよ」
「そんなの決まってるよ」
「そうか。わかったから、もう寝たらどうだ? お父さんは風呂に入るぞ」
春が来た。私たちは小学三年生になり、ちょうどその頃、NHKホールではザ・ピーナッツの
さよなら公演が行われた。小春も私も何とはなしに感慨無量で、学校でクラスメートたちと机を
寄せ合って給食を囲むときなどに、ついに引退しちゃったね、と言ったりしたが、同じ年頃の女
の子たちは皆、キャンディーズや桜田淳子に夢中だったから、ザ・ピーナッツが好きだったの?
へぇぇぇぇ、と怪訝な顔をされるのがオチだった。
「ふたごだから、やっぱ、気になるの?」
そんなときには、私たちは決まって、
「え? 別にファンってわけでもないんだけどさ」と答えた。
それでいて、小春と私は民放で『さようならザ・ピーナッツ』という特別番組が放映されるこ
とを知ると、母が、別の番組を見たい、などと言い出さないよう、あらかじめチャンネル決定権
を予約しておき、当日のその時刻には、ふたりでがっちりとTVの前に陣取った。日曜日の夜だ
ったから、父も家にいた。珍しく祖母も長沼さん宅から早めに引きあげてきて、
「何だか、ピーナッツの引退はひと事とは思えなくてね。変なものね」などと言いながら、私た
ちの隣りに坐った。母も道太郎を膝に乗せてTVの画面を指差し、
「み−ちやん、ピーナッツ、バイバイなんだって」と話しかけていた。
家族全員揃ってTVを見るなんてことは、ずいぶんと久しぶりだった。
ザ・ピーナッツは銀の縁取り、ところどころにラメが施してある、きらきらと光る真っ白なイ
ブニングドレスを身につけて現れ、デビュー曲の『可愛い花』から歌いだした。ふっくらとした
フェミニンなショートカットがとても似合っていた。それから、すぐにコマーシャルが入って、
次に現れたときには、からだにフィットする真っ赤なロングドレスを看ていて『情熱の花』と
『恋のバカンス』を歌い、また次の場面が映ったら、今度はベージュのシックな衣装に変わって
いて、その後はブリリアントグリーンのドレス……といった具合に、次から次へと衣装替えをし
て、耳に馴染みのある曲を歌い継いでいった。
ザ・ピーナッツのふたりは三十四歳になったところだったらしいが、そんなふうにはまったく
見えなかった。若々しい、とか、老けている、というのとはまた違う、年齢不詳な感じがするの
だ。『モスラ』に出演していたときの孤島の妖精のイメージを拭いきれないせいかもしれないが、
ふたりは年齢を超越しているみたいに見えた。あるときは少女のように可憐で、あるときは、あ
まりに長く生きてしまつた後のような疲れきった表情をしていた。でも、思えば、ザ・ピーナッ
ツと私たちの母親は同じ年頃なのだ。おそらく母の方がひとつ、ふたつ若いくらいだ。そのこと
にふと気がついたとき、私はどうしてかショックを受けた。
「ねえ。ザ・ピーナッツとお母さんって歳がほとんど同じだって知ってた?」と小春の耳元で囁
くと、
「あ−」と彼女は肯定とも否定とも受け取れる、間の抜けた声を上げた。
一方、祖母はしみじみとした口調で、
「ほんと、この人たち似てるわ」と言った。「似てる。こわいくらい。我が家のふたごは見慣れ
ちゃったから、もう何とも思わないけど、よそのふたごを見ると、何だかあらためてぴっくりし
ちゃうわよね。どうして、こんなに似てるのかしら?」
「どうして……って、ふたごだからですよ」と父が言った。
「でも、小春と日和の方がもっと似てるわよね」と母が言った。「ザ・ピーナッツのエミちやん、
ユミちやんはよく見れば、どっちがどっちかわかるじやない? うちの子たちはそうそう簡単に
は区別がつかないもの。そう思わない?」
「そうかな? あたしたちってそんなに似てる?」と小春が言った。彼女は道太郎が母の膝から
立ち上がり、よちよち、よちよち、と危なっかしい足取りで歩き回るのを横目で眺めていたが、
ひょいと両腕を伸ばして、そのよく肥えた胴を抱きとめると、TVの方へと顔を向けさせた。
「ほら。み−ちやん、見て。よ−く見ておくんだよ。あれがザ・ピーナッツ。お姉ちやんたちだけ
じやなくて、世の中には他にもいっぱいふたごがいるんだよ」
道太郎は素直に画面をじっと見つめた。
ザ・ピーナッツはたっぷりとしたドレープが優美な純白のロングドレスを身につけ、『恋のフー
ガ』を歌っているところだった。いつもよりいっそう気合いの入った、情感のこもった歌いっぷ
りのような気がした。絶妙のハーモニーだった。私は思わず聞きほれてしまった。
「この人たち、デビュ−したのは、たぶん十七、八の頃だから、もう十五年以上もこうして歌っ
てきたのねえ。ふぅん。ああ。私も歳を取ったわけだわ」と母は溜息混じりに言った。「あんた
たちは生まれる前だから知らないだろうけど、この人たちね、デビューしたばかりの頃はもっと
ぽっちやりしてて可愛かったのよぉ」
「今でも可愛いと思うな」と私は言った。
すると、父もすかさず、
「そうだよな。今でも可愛いよな」と言った。「もうエミちゃん、ユミちゃんのことを見れなく
なるのか。シャボン玉ホリデーも終わっちゃったし、ピーナッツも引退しちまうし。いろんなこ
とが目まぐるしく過ぎていくねえ」
「シャボン玉ホリデーって何?」と私が訊ねると、
「覚えてない? そういう歌謡番組があったのよ。クレイジーキャッツとかピーナッツが出てて、
素敵な衣装を着て洒落た歌を歌ってね、すごく人気があったの。あんたたちが生まれる前からや
ってて、ううん、それどころか、確か、お父さんとお母さんが結婚する前からやってて……」と
母が言い、
「そうそう。だって、あんたたちが結婚したのは東京オリンピックの年だったもんね」と祖母が
言った。「シャボン玉ホリデーは、オリンピックの何年か前からやってたわよ」
「そうよねえ。で、三年くらい前に終わっちゃったの。ほら、覚えてない? 日曜日の六時半か
らでね、牛がもおー! っで鳴いて始まるのよ」
そう言われてみれば、そんな番組を見たことがあるような気もした。でも、小春も私もまだ幼
稚園児だった頃のことだ。記憶はあまりさだかではなかった。
「あの番組が始まった頃は、まだTVも白黒だったよなあ」と父がしみじみとした口調で言った。
「そうそう。そうだった。TV、白黒だった」と母が言った。
「でも、時代が変わろうが、何が変わろうが、ピーナッツまで引退しなくたっていいじやないか
と思うがね。何でやめちまうんだろう? もったいない」
「あら。結婚するんじゃないの? 違うの?」と祖母が言った。
「どっちの人が?」と私が訊ねると、
「さあ。そこまでは知らないわよねえ、おばあちゃん?」と母が言った。
ザ・ピーナッツは更に何度も何度も衣装を替えつつ、メドレーで外国のポップスを歌って踊り
まくり、ゲストの人々とのトークも交え、いよいよエンディングが近づいたところで、『帰り来
ぬ青春』というタイトルの、しんみりとした曲を歌い始めた。出だしは淡々とした曲調だったの
だけれど、やがて激しく盛り上がり、エミちゃんとユミちゃんは向かい合って「さよなら ねえ
さん さよなら いもうと ふたりでひとりのじんせいともおわかれ」と熱唱した。私はぴっく
りしてしまった。
「あらまあ」と母は声を洩らした。「ふたりでひとりの人生ともお別れ、だって」、
祖母がくすくす笑った。
「小春ちゃんと日和ちゃんも、どちらかがお嫁に行くときには、これ歌うといいわね。披露宴と
かで、余興でね。さよなら姉さん、さよなら妹、って」
「そうよ。そうしたらいい。きっと拍手喝采よ。泣いちゃう人もいるかもしれない」と母が言っ
たところで、ちょうどエミちゃんが感極まって泣きだした。
「あ。ほんとに泣いた」と驚いたように祖母が言い、
「うるさいなあ。ちょっと黙って聞いたらどうなんです?」と父が憮然とした口調で言った。本
気で怒っているみたいだった。
祖母と母は顔を見合わせて、またくすくす笑い、ふたりの人の悪さに私は呆れてしまったけれ
ど、番組の最後にザ・ピーナッツの父親が登場して「ごくろうさま」と言い、エミちゃんとユミ
ちゃんが涙をぼろぼろこぼしながら、父親に肩を抱かれて『ウナ・セラ・ディ東京』を歌ったと
きには、あからさまではなかったけれど、祖母も母も心を動かされているようすだった。母は父
の方を見て、あらやだ、お父さんたら泣いてる、と憎まれ口を利くのを忘れなかったものの、実
は目を潤ませていたのは母の方だった。
小春は道太郎の手をつかみ、TVに向かって振って、
「バイバイ。バイバイ」と言った。
道太郎も笑いながら、
「ばぁばぁ。ばぁばぁ」と言った。
私は番組が終わってしまうのが、何だか少しだけつらかった。確かに、ザ・ピーナッツの歌は
父のためにさんざん歌って踊ってきたけれど、ファンというほどではないつもりだった。同じ年
頃の他の女の子たちと同じようにキャンディーズや桜田淳子の方が好きだった。でも、こうして
『さようならザ・ピーナッツ』を見ていると、実は、彼女たちが好きで好きでたまらないような気
もしてきて、いよいよ画面からふたりの姿が消えてしまうと、自分でも驚いたことに、目に涙が
滲んできた。
著作物をこんなに長く引用してはいけないとは思います。
でも、このくらいご紹介しないと素敵な本だと気付いてくれないと思いました。
当時の芸能界のことを紹介したりする本は最近多くはなりましたが、私達茶の間の
ファンの当時の感覚を蘇らせてくれる本といえば、私はこれを推したいと思います。
ザ・ピーナッツは一部の熱狂的ファンのものではありませんでした。
茶の間のまるで家族の一員のような、家の空気のような存在でした。
この小説ほど庶民におけるザ・ピーナッツ感覚をほのぼのと語っている書籍はなく、
それを売り物にしているわけではないのですが、この架空家庭の中に一緒に入って、
ザ・ピーナッツをテレビで見る思いは甘酸っぱい郷愁を感じさせます。
映画化したら(ザ・ピーナッツはテレビ画面で)いいのになあ、とも思います。
エンディングもザ・ピーナッツの歌が大切な役割を担っています。(そこは内緒)
文庫化された今、これは是非、お薦めです。
(2006.8.19記)